
脱商品化はエスピン―アンデルセンという学者が考えた概念です。
エスピン―アンデルセンは福祉国家レジームの3類型を唱えたことで有名です。

誰福祉国家レジームとはなんぞや…?
ってなると思いますが、レジームは体制という意味です。
つまり、

福祉の仕組みが国によって違うし、どうやら3つの種類に分けることが出来そうだぞ…!
と発見したのがエスピンさん(アンデルセンさん?)です。
そしてその3つに分ける際のキーワードが
- 脱商品化
- 階層化
の2つです。
『脱商品化』とは?
まずは脱商品化。
ここで言う商品=人です。
どういうことかと言いますと、私達は働いてお金を得ていますよね。
つまり、自分(労働力)を売って、給料(代金)を得ている商品な訳です。
人口ピラミッドの生産年齢人口(15歳~64歳までの人口)なんかは分かりやすいですよね。
子ども、お年寄りは生産(労働)が出来ないのでこの人口からは漏れます。
まぁようは

15~64歳は基本的に働けるよね…?
って国が思っている年齢だということです。
そこで脱商品化に話を戻しますが、この商品から脱するとはどういうことなのか…。
世の中には皆が皆、商品(労働)になれるわけではありません。
まず、障害者の方がいます。
障害者の方でも労働する方はもちろんいらっしゃいますが、全く労働出来ない方もいらっしゃいます。
そして、先程もいった高齢者や子ども。
社会には商品(労働)を担えない人が結構いるわけです。
そんな労働に参加していない人達が、どれだけ普通の生活を送れるのか(福祉が充実しているのか)の指標を脱商品化と言います。
『階層化』とは?
次に階層化。
階層化とはその福祉サービスが平等なのかどうかを見る指標です。

男だろうが女だろうが、独り身だろうが結婚してようが、同じ条件なら同じサービスが受けられます
となれば階層化は低いです。
逆に、

高所得者には手厚いサービスが出来るけど、貧乏人にはサービスはないよ
ってなると階層化が高いとなります。
福祉国家レジームの3類型とは?
『脱商品化』『階層化』の2つの指標をエスピンさんが考えた3つの類型に当てはめると以下のようになります。
| 脱商品化 | 階級化 | 例 | |
|---|---|---|---|
| 社会民主主義レジーム | 高 | 低 | スウェーデン |
| 自由主義レジーム | 低 | 低 | アメリカ |
| 保守主義レジーム | 高 | 高 | ドイツ |
社会民主主義レジームと自由主義レジームはほぼほぼ正反対な社会(いわゆる大きな政府と小さな政府です)なんですが、よく見ると階級化が同じ低いになっていますね。
これは、社会民主主義レジームがどんな人にも手厚い福祉サービスを受けることが出来るという意味で階級化が低いという意味に対し、自由主義レジームは金持ちだろうと貧乏人だろうとそもそも福祉サービスは無いよという意味です。
社会民主主義レジームの例
医療費を例にしてみましょう。
スウェーデンだと18歳まで医療費は全額無料です。
18歳以降でも上限額が決められていて外来診療だと年900クローナ(日本円で12000円くらい)以上の医療費は払い戻されます。
ちなみに日本の高額医療費制度だと、所得によりますが年収がない人でも月3万5千円以上は使わないと戻って来ません…。
自由主義レジームの例
そして、アメリカでは公的な医療保険がありません。
いや、あるにはあるんですが、メディケアという高齢者と障害者と腎臓病疾患者しか入れない医療保険になります。
それにしてもこの制度がややこしい。
パートAからパートDまであるらしいんですが、正直何書いてるのか分かりません。

アメリカ人は理解できるのだろうか…
アメリカにはケアマネージャーもいないらしいので、こんなややこしい制度が高齢者に理解できるのか本当に疑問です。

無理ゲーでは?
メディケアの他に経済困窮者になった高齢者にはメディケイド(低所得者を対象とした医療扶助)がつかえます。
メディケイドは元々シングル家庭を救済するために作られた制度らしいんですけど、今では高齢者や障がい者の低所得者も保証しているようですね。
まぁ、先程も言いましたがこのメディケア・メディケイド政策は本当にややこしい!
メディケアには色んなパターン(A~Dパターン)があるし、メディケイドは州が管轄だからなのか州によって基準が違ったりと、

もう頭痛くなります…
ただ、私fifiが一生懸命調べて分かったことは、基本的に国はお金を出したくないってこと。
もう自己責任です。
まぁでもこれもある意味、平等といえば平等。

金持ちだから国が面倒みる
なんてことはとりあえずありません。
保守主義レジームの例
そして、最後はドイツなどが代表される保守主義レジームです。
保守主義レジームは脱商品化も高いですが、階級化も高いです。
この階級化が高いというのが保守主義レジームの特徴で分かりやすく言うと、公務員だけやけに良い社会保障がされるということです。
というより、ドイツなんかは社会保障の源流がギルド(同業者組合)にあるみたいで、職業別になっているというのが色濃いみたいです。

年金や医療保障など社会保障の内容はかなり日本に近いのでは?
と思います。
貧困などの救済なども積極的に行うので脱商品化は高いのですが、なんかちょっと

不平等?
って感じてしまうのがこのレジームです。(私だけ?)
日本の場合は?
日本は自由主義と保守主義のミックスと書きました。
その理由としては、社会保障的にはしっかりしている(年金や医療保険など)部分は保守主義レジーム。
けれど、生活保護には厳しいミーンズテスト(月収○○円以下、とか車持っちゃダメ、とか)を受け、世間からのスティグマ(ネガティブなレッテル)を浴びなくてはならないというところは自由主義レジームの要素だそうです。
というか書いてて思いますけど、

ほんとカタカナの専門用語多すぎ…
以上がエスピンさんの福祉国家レジーム3類型の説明です。
しかし、もちろんこの論にも批判はあります。

3つって少なくない?もっとレジームはあるだろう
とか。
まぁ、基本的に論ずるところに必ず批判はあります。
でも

エスピンさんかなり分かりやすくしてくれたんじゃないかな?
と私fifiなんかは思うのですが、どうですかね…?
他にも「ガバナンス」の意味を説明をした記事もあるので、
ガバナンスの意味とは?福祉用語を簡単に分かり易く解説!
社会福祉士試験を勉強していると「ガバナンス」という言葉が…。となりませんか?福祉用語におけるガバナンスとはどのような意味なのか?社会福祉士の資格を取得した経験のある筆者が分かりやすく解説してみました!
良ければこちらも一緒にご覧下さい。
<参考文献>








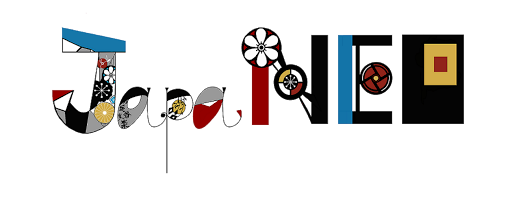
0 コメント